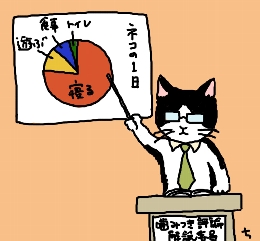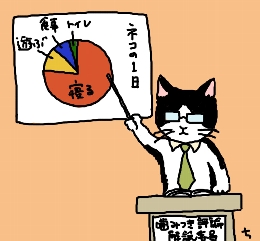|
まだ見ていないが、日米双方の視点から硫黄島攻防戦を描いたクリント・イーストウッドの「父親たちの星条旗」「硫黄島からの手紙」が話題になっている。この監督の「ミリオンダラー ベイビー」は
優れた映画だった。
ひと月ほど前、彼が「硫黄島からの手紙」の日本上映を前にして、NHKのクローズアップ現代に出演していたが、そのときの彼の発言に興味を持った。いくつか紹介
したい。
『「(硫黄島からの手紙で)当時の日本の兵士達も私達と全く変わらない、同じ人間だったということを知ってもらいたいのです」
「むなしい戦争に苦悩する兵士の姿を伝えたかったのです」
「娯楽を求める人には別の映画をお薦めします。」
「多くの若者が次々と命を落としていく中、祖国ではその帰りを待ち続ける家族や恋人達がいた。これが戦争の現実です。派手な戦闘シーンを見せるよりも、これを描き出すことが戦争
の本質を突くことになるのです」
インタビューアー、国谷裕子の「あなたの映画は厳しい批評にさらされたり、興行成績が振るわないこともありました」との発言に応じて。
「私がいいと思った映画が受け入れてもらえないかもしれません。しかし私は自分の考え方や感じ方を信じて映画を作ったいくしかないのです」
「私がもっとも気に入っている映画が最高の興行成績を上げているわけではありません。それは仕方のないことです」』(「父親たちの星条旗」の米国での興行成績は振るわなかったそうだ。)
イーストウッドの話の内容はとくに際立ったものではない。しかし、衒いのない言葉は素直に受け入れられる。
次にある月刊誌の編集者によって書かれた一文を紹介する。
『われわれ雑誌編集者は一号一号、一冊一冊が勝負だから、常に読者の興味が奈辺にあるかを意識せざるを得ない。読者の興味に迎合し過ぎることでスキャンダリズムとかセンセーショナリズムと批判されることが多いが(そしてまた批判されても仕方ないケースも少なくないが)、スキャンダリズム、センセーショナリズムが全くなくなったら、それはジャーナリズムではないとぼくは思っている。
今の新聞が失ったスキャンダリズムとセンセーショナリズム、これこそ雑誌、とくに週刊誌の命なのだ。』
イーストウッドが、自分の考え方や感じ方を信じて映画を作り、受け入れられない場合は仕方がないというのに対して、この編集者は一冊一冊が勝負だから常に読者の興味が奈辺にあるかを意識して本を作るという。
製作者の姿勢に大きな違いがある。映画と本は異なるメディアであるが、何かを伝えるという機能をもつことでは同じだ。一冊一冊が勝負だということは目標は常に販売部数だという意味なのだろう。また読者への迎合、スキャンダリズム、センセーショナリズムが大切だと述べている。メディアの商業主義の本音を正直に表しているという点で「価値ある」発言だ。
社会的事件や芸能、スポーツを扱う雑誌ならこれでかまわないと思うが、政治を扱う雑誌の場合はこれでよいのだろうか。この編集者の雑誌はこの夏あたりから靖国問題を機に、反中、反韓、反北朝鮮特集を組み、読者の興味に見事迎合したらしく、販売数を大きく伸ばした。
「硫黄島からの手紙」は相手国兵士への理解を促すことがテーマのひとつであるのに対し、この雑誌は相手国との差異を強調している。対照的である。
政治や外交は複雑な世界であり、真面目で、冷静な議論はわかり難く、面白くない。それに対して勇ましい議論、単純な二元論、煽るような議論は読者に歓迎されやすい。まさに
グレシャムの「悪貨は良貨を駆逐する」如きである。
その結果、無視できる程度の少数意見がメディアに乗せられることによって、大きな影響力を持つこともある。例えば隣国に、わが国の右傾化の懸念を抱かせることがあるかもしれない。また国内に無用な対立を招くかもしれない。
むろん言論の自由がある以上、様々な意見が発表されていい。その意味では発表された意見が特定の国の神経を逆なでしてたとしても仕方がない。先方もわが国には表現の自由があることぐらい知っている。
問題は販売部数を増やすために、つまり商売のためにスキャンダリズム、センセーショナリズムを駆使して、特定の政治思想を利用することにある。
これが有害本を生みだす仕組みである。以前にも書いたが、戦前の朝日は時勢に積極的に迎合し、勇ましい記事をふんだんに載せて戦争を鼓舞した結果、発行部数を大幅に伸ばし、毎日を抜いて第一位になった。
いろいろ事情はあったにせよ、有害新聞であった。
イーストウッドほどの非商業主義は望むべくもないにしても、政治色の強い雑誌編集者が商業主義を堂々と公言して恥じない風潮を奇異に思う。わが国のメディアの「品格」を表しているようだ。販売部数も大事な要素であることもわかるが、それは映画の興行成績でも同じだ。
販売部数を最優先としなくても編集者が安心して仕事のできる仕組みが見つかりそうにない以上、彼らの見識に期待するしかないのが現状なのである。 |