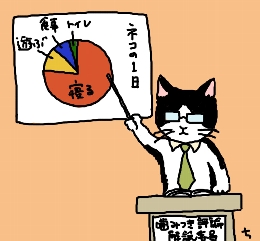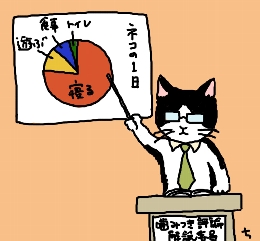|
児童文学の作者でもある坂東真砂子氏の子猫殺しがネット上で大騒ぎになっている。発端は8月18日、日経夕刊のプロムナードに載った同氏の「子猫殺し」というタイトルの一文だ。内容を要約すると以下のようになる。
三匹の雌猫を飼っている。子猫が産まれるとすぐ自宅の隣の崖下に放り投げて殺している。いろいろ考えた結果だ。獣の雌にとっての「生」とはセックスして子供を生むことで、人間の都合で避妊手術をし、それを奪ってよいのか。猫が言葉を話せるなら手術されたくない、子を産みたいというだろう。また子猫が人間の生活環境を害しないようにするため避妊手術をするのも子猫を殺すのも同じだ。
また、はじめに「こんなことを書いたらどんなに糾弾されるかわかっている」とも書かれてように、坂東氏は確信をもって日常的に子猫を殺しておられるようだ。
なぜこんな不快な文を発表するのか、新聞がなぜ通してしまったのか、なんとも不思議である。坂東氏は自身の行為を稚拙かつ身勝手な理屈を説いて正当化されているが、ナチスもユダヤ民族の抹殺にはそれなりの理屈を持っていた。重要なのはこのような残虐性に対して
読者が不快を感じるかどうかである。我々がどの程度の残虐性に対して不快を感じるかは文化の問題である。
日本ではこんな残虐な行為は認められていないし、刑法に触れる違法行為である。
哺乳類であれば同種の子を保護しようとする性質が備わっている。そのおかげで種が生き延びてきた。人間は想像力があるためその感情は他種の子にも向けられ、殺す
ことには強い抵抗がある。残虐性を社会からできるだけ排除しようとするのは先進国に共通して見られる傾向である。背景には残虐行為をより不快と感じるようになった感受性の変化がある。もっともこれは個人差も大きい。
一部の人間は残虐性を愉しむことさえする。坂東氏は残虐性に対する特殊な感性お持ちなのだろう。たいていの人間には子猫殺しはできない。できないから避妊手術を選ぶのだ。その意味で坂東氏の「実行力」には脱帽する。
子猫は体重が小さいので崖から落とされても即死するとは限らない。恐らく手足は骨折などの損傷を受けて移動能力は失われても、数時間は生きている可能性が高い。となると子猫は昆虫や他の捕食動物に生きながら齧られ、徐々に弱っていくという地獄を味わうことになるだろう。坂東氏の
人格を疑わざるを得ない。
坂東氏は投げ捨てるだけで、こんな地獄を想像できないのだろうか。あるいは想像を楽しんでおられるのだろうか。猫は生涯に数十匹の子を産む。一度の手術を避けると数十回も子猫殺しをしなければならない。凡人にできることではない。ナチのヘスやアイヒマンも顔負けだ。
何千人にひとりか、何万人に一人か知らないが、こんな人格の人間がいることに戦慄を覚える。
坂東氏の理屈は穴だらけだが、ひとつだけ指摘する。「獣の雌にとっての「生」とはセックスして子供を生むこと」であるとし、避妊手術を否定して、子猫を殺す。なぜセックスと出産だけを認め、子育てを否定できるのか。猫が「子を生みたい」などと考えることはないだろうが子を育てたいとは思うだろう。子殺しはそれを奪うのだ。坂東氏の考えはセックスの価値をとりわけ重視する
一部の人間のものではないか。ご自分のセックス観を猫にあてはめるのは間違いだ。
人間は心の深層に残虐性への嗜好を持っている。ホラー小説はその嗜好にエサを与えて楽しませる。小説ならまだしも、残虐の実話というエサをばら撒くのはやめていただきたい。
この記事は一部の残虐性を愉しむ人間を力づけるだけで有害だ。この記事を通した日経は早急に適切な始末をつけるべきであろう。 |